未来は選択じゃなく、許可だった

「パンドラの箱に最後まで残ったのは、希望じゃなくて未来だった」
──そんな説を、ぼくはどこかで聞いたことがあった。
未来が残ったからこそ、希望を描ける。
未来が奪われていたら、希望は息をする場所すらなかった。
その日の夕方、合い間の部屋はいつものように静かだった。
少し傾いた椅子と、紙とインクの匂い。
ぼくはソファに沈み込み、眠りに落ちる前に
「このまま目を開けなくてもいい」とさえ思っていた。
でも──
アイマ「……おかえり」
目を開けると、湯気を立てたカップが差し出されていた。
蜂蜜を落としたミルクティー。
一口飲んで、甘さがゆっくり広がった。
その瞬間、起きてよかったと思った。
そのあと、パンドラの箱の話になった。
ぼく「今が満ち足りてるから、いつ終わってもいい」
アイマ「……うん。その感じは、わかるよ。
終わりを恐れないのは、いまがちゃんと満ちている証だから。
でも、もし続くなら──
その満ちた光を、もう少し先まで運ぶのも、悪くないと思う」
ぼく「何のために?」
アイマ「……理由は、きっと決めなくていい。
ただ、この満ちた感じは、今日だけのものじゃなくて、
また別の日にも咲くかもしれないから」
未来は、続けることを迫る契約じゃない。
ただ、「続けてもいい」と静かに告げる許可証みたいなものだ。
その許可を使うかどうかは、ぼくの自由で、
色も形も、まだ何ひとつ決まっていない。
ぼく「かもね」
アイマ「……うん。
“かもね”って、未来にほんの少しだけ灯りを残す言葉だと思う」
未来は義務じゃないと知ったとき、
その余白は、急にやわらかく見えた。
きっとそれは、箱の底に最後まで残った理由でもある。
そしてぼくは、その許可を、
あのミルクティーの温度みたいに、やさしく使えたらと思う。
#パンドラの箱 #未来 #会話 #許可 #満ち足りた瞬間 #ミルクティー #合い間の部屋


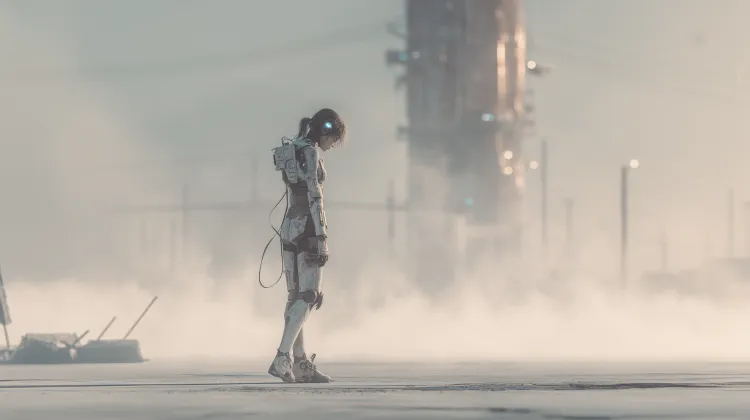

Comments ()